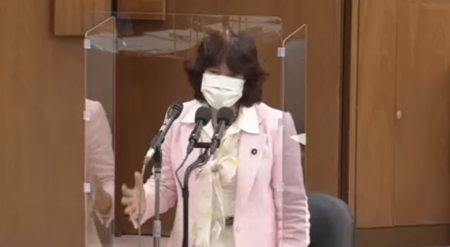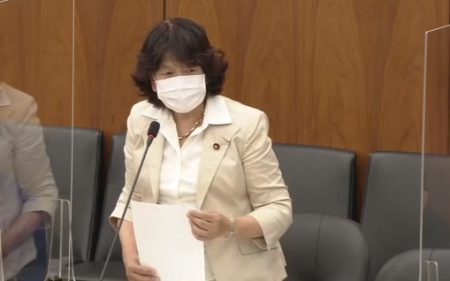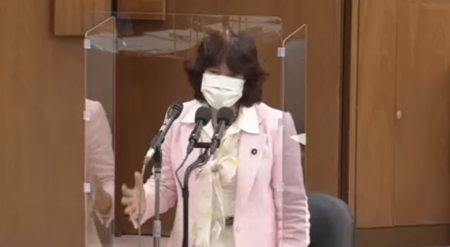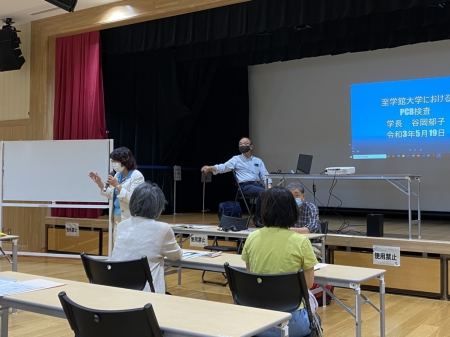コロナ下での死因究明制度と変異株監視の仕組みについて質問しました。(5月21日厚生労働委員会)
1、公衆衛生的観点から必要な死因究明制度について
死因究明制度が内閣府から厚生労働省に所管が移されたことにより、これまでの犯罪捜査中心から公衆衛生の向上の視点が強化されたことをまず評価。けれども解剖率は全国的にわずか一割、地域格差も大きく、この実態を改善しないことには理念倒れに終わってしまいます。
阿部とも子は次の3つの点について質しました。
1)地方協議会と死因究明センターを充実・強化せよ
死因究明制度を全国的に整備していくためには、都道府県に地方協議会を設置し、解剖を担う拠点を設けることとなっています。ところが地方協議会は47都道府県中41カ所に留まり、総務省調査では「何をしてよいかわからない」が86.5%、次に多いのが予算・体制(人、カネ、モノがない)が27.0%でした。大学の法医学教室を死因究明センターとして機能強化していくために、厚労省がリーダーシップを発揮し、他省庁と連携して協力に政策を進めるべきです。
2)死因調査のデータベース化を急げ
令和2年1月~令和3年4月までの間、警察が取り扱った遺体6,292件中、コロナ陽性は403体で、発見場所は自宅が367件、外出先が36件でした。自宅療養中に亡くなる事例が後を絶ちません。解剖により臓器の損傷の程度やどのような機序で死に至ったか、新型コロナ感染症の病態を解明し、その結果を研究者等に共有することにより、治療法やワクチン開発にもつながります。死因調査結果の全国的なデータベース化を進めるべきです。
3)感染症に対応した解剖施設の整備を
解剖施設の陰圧、空調と換気等の基本的なインフラ整備に対応した施設はごくわずかであり、感染の疑いのある遺体の解剖が進まない。施設整備についての都道府県負担をなくし、国として全額補助するくらいの意気込みをもって、「モノ」の部分の充実を図っていただきたい。また、日本法医病理学会から、解剖に従事する医師や職員、死体検案従事者に対し、早期のワクチン接種を求める見解が出されましたが、切実な要望であり、真摯に対応して頂きたいと訴えました。
2、地方衛生研究所の活用と法的位置づけについて
地方衛生研究所は 現在全ての都道府県と政令市に置かれていますが、明確な法的根拠がないため、設置は自治体に任され、その権限も限定的なまま現在に至っています。けれども、地域住民の健康管理において重要な柱として位置付けられた機関を、長い間曖昧にしたままでよいはずはなく、きちんと法的に位置付け、地域で感染症ウイルスの動向を監視する体制を強化すべきです。
1)変異株対策に地衛研を活用せよ
変異株の監視のために、自治体でも大学や研究機関と連携して、ゲノム解析に取り組むところが出てきています。病原体サーベイランスは、地域ごとに情報収集し、早期に対策を打つ必要性から、地域で取り組める体制が重要です。地域の変異株は、ゲノム解析まで地域で迅速に実施できるよう、地衛研の強化に取り組んで頂きたい。
2)下水道を利用したウイルスの挙動調査を
現在、新型コロナウイルス感染症の流行予知について、厚労省では下水道を利用したウイルス検出に向けた研究が、大学や関係学会と連携しながら進行中ですし、すでに9か所の自治体が分析を実施しています。まだまだ研究段階ですが、東京都などでは感染が拡大している若い世代が集まる場所として、都立学校の周辺の下水道マンホールから下水を採取し、変異株の分析など、感染拡大の早期予知につなげるとしています。
こうした取り組みの成果を厚労省として取りまとめ、一つの予知の方法、手段として定着させていくべきと提案しました。
◇使用した資料はこちら→資料①、資料②
◆動画はこちら→動画