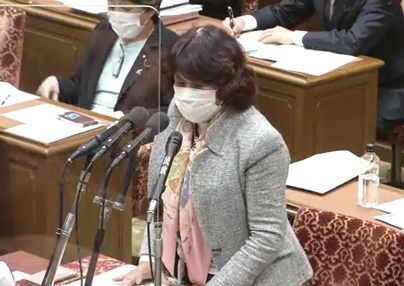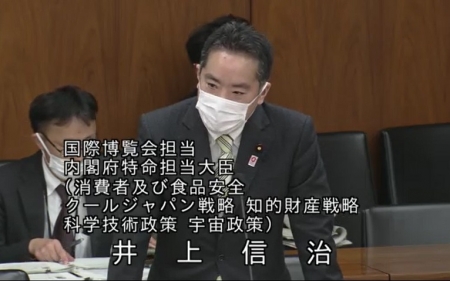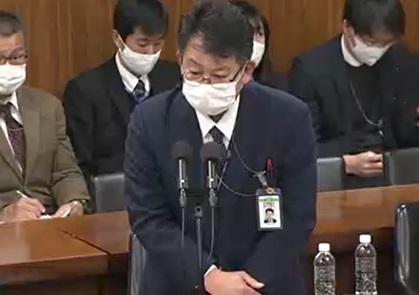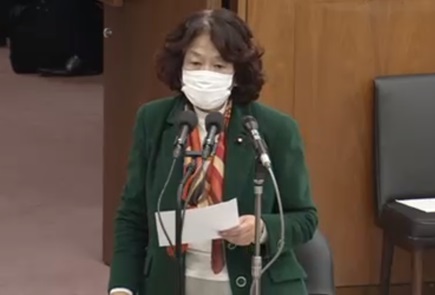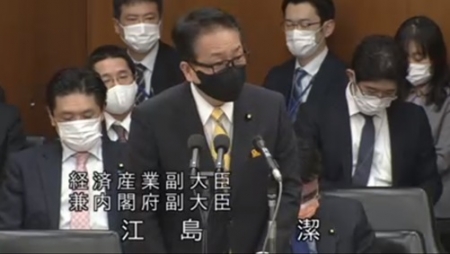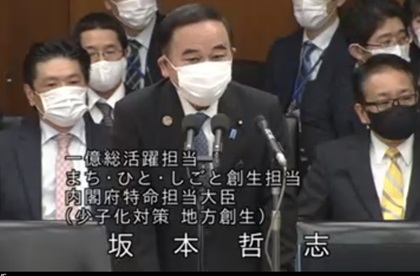阿部知子が令和3年2月24日に提出した『公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問主意書』に対する答弁書が、令和3年3月5日、閣議決定されました。
以下質問全文と回答(赤字)は以下の通り。
我が国における死因究明制度は、二〇一二年に「死因究明等の推進に関する法律(以下、推進法)」と「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下、調査法)」が成立し、調査法に基づく新たな解剖制度が創設されたことで大きく前進するかに見えた。しかし推進法は時限立法のため二〇一四年に失効し、しばらく理念法の空白状態が続いたが、ようやく二〇一九年に新たに成立した「死因究明等推進基本法(以下、基本法)」によって設置された死因究明等推進本部において、死因究明等推進計画の策定に向けた検討会が継続されている。この経緯を踏まえて以下質問する。
一 死因究明に関する施策は、従来の推進法では総合調整的な役割が必要とされ、内閣府の所管とされたが、二〇二〇年四月一日に施行された基本法では、厚生労働大臣を本部長とする死因究明等推進本部に所管が移された。推進法の成果はどのように評価され、どのような経緯で厚労省の所管とされたのか。
一について
政府としては、死因究明等の推進に関する法律(平成二十四年法律第三十三号。以下「推進法」という。)の規定に基づいて作成した死因究明等推進計画(平成二十六年六月十三日閣議決定。以下「旧計画」という。)に基づき、関係省庁において各般の施策を進めてきたところであり、お尋ねの「推進法の成果」については、我が国における死因究明及び死体の身元確認(以下「死因究明等」という。)の実施体制の充実に一定の役割を果たしたものと考えている。
また、お尋ねの「経緯」については、平成二十六年九月に推進法が失効した後も、引き続き死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和元年六月に死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号。以下「基本法」という。)が制定され、公衆衛生の向上が基本法の目的の根底にあると位置付けられたことから、基本法第二十条において、厚生労働省に死因究明等推進本部を置くこととされたものと承知している
二 推進法において「実施されるべき施策」の第一に掲げられた「死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備」については、ほとんど進捗がなかった。このことについて、課題はどのように総括され、その結果が基本法及び現在策定中とされる「死因究明等推進計画」にはどのように位置付けられているのか。
二について
御指摘の「死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備」については、旧計画に基づき、令和三年二月時点において、三十九都道府県に死因究明等推進地方協議会が設置されており、一定の成果があったと考えているが、基本法第十二条において「国及び地方公共団体は、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しつつ、法医学、歯科法医学等に関する知見を活用して死因究明等を行う専門的な機関を全国的に整備するために必要な施策を講ずるものとする」と規定されていることを踏まえ、現在、当該必要な施策の位置付けを含め、基本法第十九条に規定する死因究明等推進計画(以下「新計画」という。)の策定に向けた検討を進めているところである。
三 二〇一二年から現在までに警察が取り扱った遺体のうち、司法解剖、行政解剖(監察医解剖・承諾解剖)、調査法解剖に付した数の年次推移について、政府が把握しているところを都道府県ごとにそれぞれ示されたい。聞き及ぶ限りではこの期間に剖検数も地域差も大きな改善はないと認識しているが、この結果をどのように分析したのか。
三について
平成二十四年から令和二年までの各年において警察が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、①司法解剖を実施したものの数、②警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第六条第一項の規定による解剖(以下「調査法解剖」という。)を実施したものの数、③その他の解剖(死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定による解剖及び遺族の承諾を得て行う解剖をいう。以下同じ。)を実施したものの数を、政府が把握している限りにおいて都道府県別にお示しすると、次のとおりである。
※別紙参照
(最後の頁に添付した資料をご覧下さい。)
司法解剖及び調査法解剖については、都道府県警察等において、それぞれの事案ごとに、死体及び現場の状況、各種検査の結果、立ち会った医師の意見等を勘案し、個別に解剖の要否が判断されたものと承知している。
その他の解剖については、司法解剖や調査法解剖が行われないが、死因を明らかにするため、死体の検案を行った医師が必要と判断した場合等に行われたものと承知している。
四 欧米の先進国の多くが、死因究明の最終目的を「国民の健康と安全の増進」としている。一方、日本においては、解剖の要否を決める判断基準は事件性、犯罪性の有無であり、医学的、衛生学的視点で解剖を行うことは原則ないとされ、警察主導の制度となっている。さらに、司法解剖は原則非公開のため剖検情報が共有されず、事件の再発防止や公衆衛生には活かされにくい実態があるが、死因究明の目的について、基本法においては何と位置付けられているのか。
五 基本法は基本理念として第三条第二項で、「死因究明の推進は(中略)死因究明により得られた知見が疾病の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されることとなるよう、行われるものとする」と定めている。
現在、拡大の一途をたどっている新型コロナウイルス感染症などの新興感染症対策は、まさしく公衆衛生上の最も重要な目的の一つと考えるが政府の見解は如何。
四及び五について
政府としては、基本法第三条第二項において「死因究明の推進は、高齢化の進展、子どもを取り巻く環境の変化等の社会情勢の変化を踏まえつつ、死因究明により得られた知見が疾病の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されることとなるよう、行われるものとする」と、同条第三項において「死因究明の推進は、災害、事故、犯罪、虐待その他の市民生活に危害を及ぼす事象が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び予防可能な死亡である場合における再発の防止その他適切な措置の実施に寄与することとなるよう、行われるものとする」と規定されていることから、死因究明により得られた知見を御指摘の「新興感染症対策」を含む公衆衛生の向上及び増進に資する情報として活用することは、死因究明の重要な目的の一つと考えている。
六 本年二月十七日の衆議院予算委員会において、警察庁は令和二年三月から令和三年二月十日までに警察が検視等により取り扱った新型コロナウイルス感染症陽性であった遺体二百六十一件のうち、新型コロナウイルス感染症百十四件、肺炎五十一件、その他四十七件、不詳九件、合計二百二十一件を内因死、外因死三十二件と答弁している。しかし、その多くは検案医が外表検査のみで判断した病名である可能性が高い。そもそも同期間に警察が取り扱った遺体は何件あったのか。そのうち解剖されたのは何件か。また、PCR検査を行ったのは何件か。政府の把握しているところについて答弁を求める。
六について
お尋ねの期間において警察が取り扱った死体の数及びそのうち解剖を実施したものの数については把握していない。
なお、政府が把握している限りにおいては、令和二年中に警察が取り扱った死体の数については、十六万九千四百九十六体であり、このうち、解剖を実施したものの数については、一万八千三百三十九体である。また、お尋ねの期間において警察が取り扱った死体について、PCR検査等の検査が実施された件数については把握していない。
なお、政府が把握している限りにおいては、令和二年三月から令和三年一月までの間において警察が取り扱った死体について、検案等を行う医師の判断により新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の検査が実施された件数については、四千百五十八件である。
七 新型コロナウイルス感染症は急速に進行する呼吸不全や血栓塞栓症による原因不明の突然死という転帰をとることが明らかになっている。自宅や救急搬送後に亡くなったご遺体の中に、新型コロナウイルス感染症の感染事例が見逃されている可能性は否定できない。検査や解剖を行わず、外表のみで病名を決定するこうした実態は、長期的には死亡統計にも影響を与えかねないと懸念されるが、この点について政府の見解を示されたい。
七について
「長期的には死亡統計にも影響を与えかねない」との御指摘については、死因の特定には様々な要因が影響するものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
なお、政府としては、御指摘の「新型コロナウイルス感染症の感染事例」に限らず、必要な検査、解剖等を行うことにより正確な死因を特定することは公衆衛生の向上等の観点から重要であると考えており、死因究明がより正確かつ適切に行われるよう、死因究明の実施体制の充実に必要な施策について、現在、新計画の策定に向けて検討を進めているところである。
八 感染症における公衆衛生を担う保健所は、自宅や搬送中の死亡者に対しても行政検査を行い、新型コロナウイルス陽性であった場合は、その方のご家族やご遺体に触れた警察官や検視官、葬儀関係者などに対し、積極的疫学調査を行う義務があると考えるが、それらは現状どのような実態にあるか把握しているか。
また、保健所の抜本的な体制整備の必要性をどのように認識しているのか。
お尋ねの「実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「積極的疫学調査」については、国立感染症研究所が作成した「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」等を踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十五条の規定に基づき、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の長を含む。)が必要があると認めるときに、同条に規定する者に対して行われているものと考えている。
また、政府としては、感染症対策に係る保健所の体制整備は重要であると考えており、「新型コロナウイルス感染症に関する保健所体制の整備と感染拡大期における優先度を踏まえた保健所業務の実施ついて」(令和三年一月八日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、都道府県等に対し、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するため、保健所体制の改編や増員等の全庁的な取組を推進すること」等を求めている。さらに、「保健所に係る「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」について」(令和二年九月二十五日付け健健発〇九二五第一号・健感発〇九二五第一号・総財調第二十五号厚生労働省健康局健康課長及び結核感染症課長並びに総務省自治財政局調整課長連名通知)において、「都道府県単位で潜在保健師等を登録する人材バンク」を創設することとしたほか、保健所において感染症への対応に係る業務に従事する保健師の増員に係る経費について地方財政措置を講ずる等の施策を実施することとしている。
九 法医学教室を持つ大学によっては、遺体解剖の前にPCR検査を自前で行い、医師等の安全確保を図っている大学もあると聞くが、そもそも検査費用は行政検査として当然公費から支弁すべきものである。また、解剖に当たる医師等に対しては、包括支援交付金による慰労金等は支給対象外であるという。「患者」が生者と死者で違うのは不合理ではないか。改善すべきと考えるがどうか。
九について
御指摘の「行政検査」は、感染症法第十五条の規定に基づき、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときに行われるものであり、御指摘の「医師等の安全確保」を目的に行われるものではないため、「医師等の安全確保」のために行われる検査の費用を公費により負担することは困難であると考えている。一方で、異状死死因究明支援事業において、都道府県知事が必要と判断し、大学等と連携して実施した解剖やその解剖に伴う検査については、これらの費用を補助することとしており、PCR検査についても、この対象に含まれるものである。
また、御指摘の「包括支援交付金による慰労金」については、新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと等を踏まえ、医療機関に勤務する医療従事者等を対象としているものであり、解剖のみに従事し、新型コロナウイルス感染症に感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴わない者が対象とならないことについて、「不合理」との御指摘は当たらない。
十 ところで、現在、日本では感染防止対策に対応した解剖施設はわずかしかない。最大の設備を誇る東京都監察医務院でも、医師等の安全に配慮して新型コロナウイルス陽性患者の遺体の解剖は行っていないと聞く。解剖室の陰圧、空調と換気、防護服装着のための前室等の設置など、基本的なインフラ整備がおろそかにされているのではないか。こうした剖検体制の整備については、国として十分な予算をつけて早急に取り組むべきと考えるが、どうか。
十について
死亡時画像診断システム等整備事業において、都道府県に対し、異状死体の死因究明に関して中核的な役割を果たす施設等の整備に係る費用を補助しているところであり、引き続き、こうした取組を通じて、地域における死因究明の実施体制の充実に取り組んでまいりたい。
十一 剖検情報は、感染症の病態やその経過、臓器の障害などに対する知見や治療法の開発などに重要である。新型コロナウイルス感染症に関しても二〇二〇年二月に中国から発表された肺の組織所見に始まり、世界各国からびまん性肺胞障害、血栓塞栓症、血管内皮細胞障害等の病態の解明と治療につながる重要な剖検情報が世界各国から報告されている。
日本でも新興・再興感染症対策を視野に入れた剖検情報のデータベース化と共有化は喫緊の課題である。しかし、現在の日本において公衆衛生目的で解剖を行うのは監察医解剖だけであるが、監察医制度があるのは東京都二十三区、大阪市、神戸市の三自治体のみである。これをどのように拡充していくのか、あるいは別途新たな制度を作るのか。また、死因究明等推進計画に人材育成をも含めた中・長期的なビジョンを明確に盛り込むべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
十一について
解剖等による死因究明の実施体制の充実については、死因究明に係る人材の育成等に必要な施策も含め、現在、必要な施策について、新計画の策定に向けて検討を進めているところである。
※三 添付資料 都道府県別死体取扱状況PDF こちら