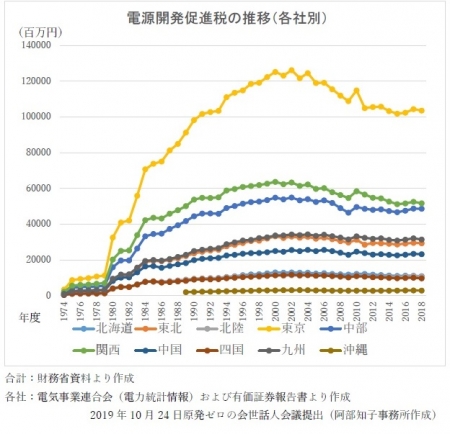カジノ管理委員会の人選見直しに関する質問主意書を提出
11月22日、阿部知子は「5人のカジノ管理委員会の候補の見直しに関する質問主意書」を提出しました。政府が11月13日に国会に提出したカジノ管理委員会の人事案が、国民から信頼を得られる人選とは到底思えないものだったからです。
質問は次の通りです。
1.任命権者である安倍晋三内閣総理大臣の見解を問いました。
「カジノ管理委員会」の委員長候補である元防衛監察監の北村道夫氏は、陸上自衛隊が破棄したとしていた南スーダン国連平和維持活動部隊の日報が、実は存在し、隠ぺいされていた事件が明らかになった当時の防衛監察監です。
防衛監察本部は、「防衛監察を通じて各部隊・機関の問題点を発見し改善策を助言するとともに、不正や非違行為につながる行為を未然に防止する」(同本部ウェブサイト説明より)役割を持ち、防衛監察監はそのトップです。
隠蔽されていたのは、日報に「戦闘」という言葉が使われる一方で、稲田朋美防衛大臣(当時)が国会で「戦闘行為が行われるような場合、この場合はPKO五原則に抵触をしてくる、すなわち憲法上の問題が起きる」(2017年2月14日衆議院予算委員会)とし、「戦闘」を「大規模な武力衝突」と言い換えて答弁を行っていた時期。
「戦闘」の文字が書かれた日報の隠蔽に、大臣がどのように関与していたのかが、国民の大きな関心事でした。
防衛監察本部は特別防衛監察を行い、2017年7月27日に「特別防衛監察の結果について」を発表。しかし、稲田大臣は調査の対象外、監察のための「面談対象者一覧」の欄外に、「防衛大臣から事実関係の解明のため協力を得た」とだけ書かれていました。
この時、稲田大臣から事実聴取をした人物が、元福岡高等検察庁検事長であった北村道夫・防衛監察監(当時)であったとされています。
稲田大臣は直後に辞任し、安倍政権はこの事件の幕引きを図りましたが、その翌年4月になり、やはり調査の対象外だった防衛省情報本部からも新たに日報が見つかったことから、国民の不信はまったく解消されていません。
国民の疑念を晴らすことができなかったことが明確でありながら、同人物をカジノ管理委員会の委員長に任命することは不適切ではないか。任命権者である安倍晋三内閣総理大臣の見解を問いました。
2. 菅義偉官房長官の関与について問いました。
カジノ管理委員候補の元警視総監の樋口建史氏は、2013年1月まで警視総監を務めた後、2014年にはミャンマー大使に就任しましたが、その就任には菅義偉官房長官が大きく関わったとされています。
これは事実なのか。また、樋口建史氏のカジノ管理委員会人事案にも、菅義偉官房長官が関わっているのかを問いました。
3. 審議会に関する閣議決定違反について問いました。
5人のカジノ管理委員候補の3人までが、1999年4月27日に閣議決定した「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」で「厳に抑制する」とした「府省出身者」です。
まったく抑制されていません。先に述べた二人の他、元国立印刷局理事長である氏兼裕之氏は、大蔵省(財務省)や国税局長の他にも通産省、厚生労働省を歴任。さらに、渡路子氏にも、厚生労働省での勤務経験があります。
それにもかかわらず、3人の「府省出身者」や1人の府省勤務経験者を任命するとすれば、それぞれ余人を持って代えがたいとする根拠をはっきりと示す必要があるがどうかを問いました。
4. 原則3、上限4の審議会の兼職も閣議決定違反。
1999年閣議決定の「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」では、審議会の兼職は「原則として最高3」、「特段の事情がある場合でも四を上限」としています。
ところがカジノ管理委員会候補の遠藤典子・慶應義塾大学大学院特任教授は、先に提出した「カジノ管理委員会の人事に関する質問主意書」でも問いましたが、それ以上の審議会をかけ持ちしています。
この人事は全面的に見直しをするべきではないか、任命権者である内閣総理大臣に問いました。