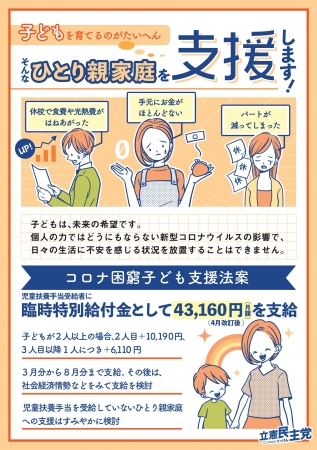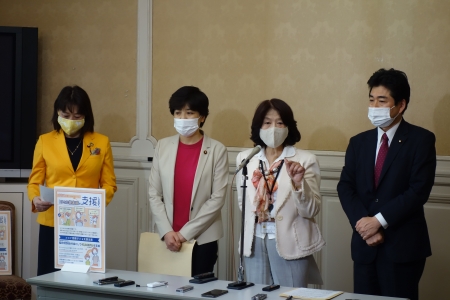阿部とも子が4月17日に提出した「カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書」への
答弁が本日(28日に)閣議決定されました。質問と答弁概要(赤字)は次の通りです。答弁の全文はこちらです(PDF)
============
カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書
国土交通省は、いわゆるIR整備法に基づく基本方針案を昨年九月に(そのうち区域整備計画の認定申請期間については昨年十一月に)パブリックコメント(以後、パブコメ)にかけたが、その後、IR(統合型リゾート)利権を巡って国会議員が逮捕され、今年一月末に公表を予定していた成案の決定を先延ばしにしている。
この間、国においては政府関係者とカジノ事業者との接触ルールを基本方針に盛り込むなどの見直しも進んでいると聞く。その後、横浜港に停泊していた外航クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で新型コロナウイルスの感染が拡大し、世界各地で緊急事態宣言などによる経済停滞が発生している。
もとよりカジノ先進国ではカジノ事業の赤字や倒産が問題となっていた。また日本では新型コロナウイルスの感染拡大前でさえ、多くの世論調査で、国民の過半がカジノ推進には反対であったため、これを機に直ちにカジノを含むIR整備は中止すべきである。少なくとも新型コロナウイルス感染拡大による新たな影響や情勢を踏まえた根本的な見直しを行う必要がある。
そこで以下、質問する。
一 国土交通省の基本方針案は、今般の新型コロナウイルス感染拡大による影響や倒産や赤字問題の情報を収集、把握、分析、総括をした上で、改めて案を出し直し、パブコメにかけ、国民の賛意が得られるのかどうかを判断すべきではないか。
二 複数の自治体では、国土交通省の基本方針の成案決定前から実施方針案や区域整備計画案を作ろうとしているが、国が基本方針案を出し直し、パブコメ終了後に、成案に則って手続を行うよう、全ての自治体に徹底させるべきではないか。
一及び二について
法に基づいて認定の申請に向けた準備作業を進めている。
三 政府は「観光先進国」を目指して「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」(議長:内閣総理大臣)を設置し、二〇一六年三月に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定した。ビジネスイベント(MICE)の誘致やクルーズ船受入の更なる拡充を謳い、二〇二〇年に訪日クルーズ旅客を五百万人にするとの目標を立てた。
また、同年六月に閣議決定した「日本再興戦略二〇一六」でも「訪日クルーズ旅客二〇二〇年五百万人に向けたクルーズ船受入れの更なる拡充」を書き入れた。ここでもMICE誘致の促進を謳い、「総合型リゾート(IR)については(略)IR推進法案の状況やIRに関する国民的な議論を踏まえ、関係省庁において検討を進める」とした。さらに「クルーズ船向け旅客ターミナル施設及びMICE施設については、公共施設等運営権方式を活用したPFI事業の案件数に係る数値目標の設定を行う」としていた。
二〇一七年六月には、「外航クルーズ船の我が国への安定的な寄港が維持できず、「訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人」とした政府目標を達成できないおそれ」があると説明して港湾法改正を行なった。その第二条の三で、外航クルーズ船の受入拠点である「国際旅客船拠点形成港湾」を国土交通大臣が指定し、指定された港湾の管理者が民間事業者と協定を結び、その民間事業者が港湾の係留施設を優先的に使用することを可能にした。
そして、この間、二〇一六年十二月にはいわゆるIR推進法が、二〇一八年七月にはIR整備法が、与党による強行採決で成立した。
言うまでもなく、カジノを含むIRでMICEを誘致することと、訪日クルーズ旅客を増やすことは、与党政府が多数決で進めてきた国策としての観光政策であった。
しかし、新型コロナウイルスが国際的に蔓延した今、政府のこうした観光政策や目標にも、抜本的な見直しが必要ではないか。
三について
政府としては、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束し、国民の不安が払拭された後には、反転攻勢し、官民を挙げたインバウンド復活への取組を進めていく考えである。
四 基本方針案の具体的な見直しについて
1 四月十五日に発表された二〇二〇年三月の訪日外客数の推計値は、前年同月比九十三パーセント減で、約二百八十万人から約十九万人へと激減した。激減の最大の要因は、新型コロナウイルスの感染拡大によるものだと考えるが、それがいつ収束すると政府は考えているか。
四の1について
お尋ねについては、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたい。
2 四月十三日の衆議院決算行政監視委員会で青柳陽一郎議員がIR整備のスケジュール延期について質問したところ、赤羽国土交通大臣は、区域整備計画の認定申請期間(二〇二一年一月から七月)について、「自治体は粛々と準備を進めている状況であり支障になっていないと聞いている」旨を答弁した。
しかし、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業募集要項」を既に公表していた大阪府と大阪市は、三月二十七日に「今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点や、これに伴い民間事業者における事業活動の縮小等が生じている状況等を踏まえ、提案審査書類の提出期限を含む今後のスケジュールを次のとおり変更します」として各手続を三ヶ月延期した。
四月十五日には、横浜市でも実施方針公表時期を六月から八月に変更すると発表した。こうした自治体の状況を鑑みれば、区域整備計画の認定申請期間は延期するのが当然ではないか。
四の2について
現時点においては、これらの都道府県等から当該期間の案を変更して欲しい旨の要望は受けていない。
3 カジノ先進国である米国では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、九割以上のカジノが閉鎖されているとの報告もあり、感染症に対する事業継続性の脆弱性は明らかである。収益をカジノに頼る区域整備計画に、いわゆるBCP(事業継続計画)やBCM(事業継続マネジメント)を盛り込むことを義務化することを基本方針で定めるべきではないか。
四の3について
区域整備計画の認定の申請を行うに当たっては、設置運営事業等について安定的な経営が可能であり、業績が下振れした場合にも適切に対応し、長期的に設置運営事業等を継続できること等について、厳正に審査を行うこととしている。
五 IR整備法第九条は「都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる」としている。
先述した四月十三日の委員会質問で青柳議員は、横浜市は「災害リスクが発生した場合は、自治体と事業者は共同事業者であり負担については事業者だけに負わせられない」旨を市議会で答弁しているとの例を挙げ、今回のように新型コロナウイルスで大打撃を受けた場合、自治体が税金を投じて事業者を救うことについて質すと、赤羽大臣は、「今般のような新型コロナウイルス感染症や自然災害のような事態への対応については、自治体とIR事業者の合意に従うことになる」旨を答弁した。
1 国土交通大臣は、国民に向けて、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があると説明したことがあるか。
2 政府は、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があると国民の何パーセントが認識していると考えているか。
3 国土交通省が、昨年九月にパブコメにかけた基本方針案には、感染症や自然災害などの事態には、自治体が税金を投入してカジノ事業者を救済する場合があるとの記載はあったか。記載があるのであれば、その箇所を明らかにされたい。記載がないのであれば、その理由を明らかにされたい。
4 感染症や自然災害などの事態を含むいかなる事態でも、経営難や赤字になった場合には、自治体が税金を投じてカジノ事業者を救済することは禁じることを基本方針案に明記して出し直すべきではないか。
五について
IRは事業者等により一体として設置、運営されるものであり、御指摘の「経営難や赤字になった場合」でも、事業者等が自ら経営改善を図ることが基本であると考えている。また、御指摘の「感染症や自然災害などの事態」への対応については、認定都道府県等と事業者等とが十分に協議した上で決められるべきものと考えている。