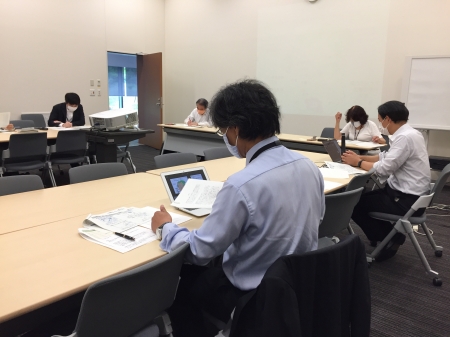除染なき避難指示解除の政府方針は、原発事故前の基準と矛盾
除染なき避難指示解除の政府方針は、原発事故前の基準と矛盾
6月11日に行った原発ゼロの会のヒアリングをもとに、翌12日に提出した「除染なき避難指示解除の政府方針に関する質問主意書への答弁書 が閣議決定されました。政府が新たに検討を始めた避難指示解除の政府方針は、原発事故前の基準と矛盾していることが、明らかになりました。
除染なき避難指示解除の政府方針に関する質問主意書
(と答弁概要)
経産省、環境省、復興庁は、飯舘村からの要望があったことを前提に、除染せずに避難指示区域の解除(以後、解除)ができるようにすることで一致し、原子力規制委員会にその安全性について諮った結果を受け、今夏にも原子力災害対策本部(本部長・安倍晋三首相)で、新たな解除要件を加える旨が、先ごろ報道された。そのため、さまざまな観点から政府の考え方を確認するため、六月十一日に原発ゼロの会はヒアリング(以下、ヒアリング)を開催した。ヒアリングでは、飯舘村の要望は決して「除染せず」ではなかったことが確認された他、現行の避難指示解除の三要件が確認された。
・空間線量率で推定された年間積算線量が二十ミリシーベルト以下になることが確実であること
・日常生活に必須なインフラ、生活関連サービスが概ね復旧すること、及び子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること
・県、市町村、住民との協議
その決定資料をたどると、二〇一一年十二月二十六日に原子力災害対策本部が決定した「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」である。
この三要件に関し、ヒアリングでは、一番目の「二十ミリシーベルト以下」は高すぎるという意味で有識者から異論があがり、二番目については、帰還困難区域は「子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗」とあるが、子どもが住めるような状態なのかとの疑問が呈された。三番目に関して飯舘村を例にあげて「地元とは何を意味するか」との問いに、内閣府原子力被災者生活支援チームが「首長、村議会、住民である」旨を回答した。
このような三要件であるから、見直す場合には、慎重な検討が必要である。
そこで以下質問する。
一 そもそも現在の三要件はどのようなプロセスのもとで決定に至ったのか。関係省庁、原子力規制委員会、原子力災害対策本部の関係性や決定プロセスがわかるように明らかにされたい。
一について
御指摘の「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」は、
2011年8月4日に原子力災害対策特措法第25条第5項(当時)に基づく、原子力災害対策本部長たる総理大臣が、緊急時避難準備区域、計画的避難区域及び警戒区域において、その見直しを含めた緊急事態応急対策を実施すべき区域のあり方及びその区域内の居住者等に対し周知させるべき事項について、原子力安全委員会の意見を求め、
これに対し、同日に同委員会が述べた意見である「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故における緊急防護措置の解除に関する考え方について」を踏まえ、
同年12月26日に原子力災害対策本部において決定したものである。(略)
二 解除要件の見直しについての政策決定プロセスは、一に対する答弁と同様のプロセスをたどるのか。そうでないとすればどのようなプロセスを想定しているのか。
二、四及び八について
令和2年2月26日の飯舘村からの「「長泥地区」帰還困難区域特定復興・再生拠点区域外の整備に関する要望書」への対応については、「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」および令和2年5月28日の与党からの「帰還困難区域(特定復興再生虚て区域外)の政策の方向性検討に係る申入れ」を踏まえ、現在検討を進めているところであり、
御指摘のように「今夏にも解除の方針や要件を見直すこと」を決定した事実はなく、また、そのような仮定を前提としていると思われる御指摘の「政策決定プロセス」に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
三 二〇一三年十一月二十日には原子力規制委員会の「帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム」が「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」をまとめ、それが解除と特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定について定めた二〇一七年五月のいわゆる「福島復興再生特措法」の改正へとつながった。この認識で間違いはないか。違うとすれば、二〇一七年五月の福島復興再生特措法改正に至る政策決定プロセスを明らかにされたい。
特定復興再生拠点区域復興再生計画に係る制度は、「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」および「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を踏まえ、当該制度の創設等を内容とする福島復興再生特別措置法一部改正法案を閣議決定し、平成29年5月12日に成立したものである。
四 解除要件の見直しについての政策決定プロセスは、三で答弁するプロセスをたどるのか。そうでないとすればどのようなプロセスを想定しているのか。また、この政策決定プロセスに原子力規制委員会はどのように関係することが、想定されているのか、明らかにされたい。
「二、四及び八について」で回答
五 帰還困難区域の解除については、福島復興再生特措法で「特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定」(第十七条の二)という形で規定されているが、「特定復興再生拠点区域」外についての定めはない。この認識に間違いはないか。
特段の定めはない。
六 福島復興再生特措法の運用上の住民の放射線防護レベルは、いわゆる「原子炉等規制法」が原子力事業者に求めている周辺監視区域の線量限度である年間一ミリシーベルトとは矛盾があるが、今後、どのようにこの矛盾を解消していくのか。
「特定復興再生拠点区域における放射線防護対策について」の長期目標と線量限度とは、性格が異なるものである。
七 ヒアリングにおいて、内閣府原子力被災者生活支援チームは、特定復興再生拠点区域内においては、子どもが十分に生活できるレベルを前提に除染をしている旨を回答していたが、そのレベルとは、具体的に空間線量率で毎時何マイクロシーベルトを目安としているのか。
内閣府原子力被災者生活支援チームは、「特定復興再生拠点区域の避難指示解除と期間・居住に向けて」における避難指示解除の要件の一つ「子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること」の趣旨を説明したものである。当該要件においては、除染作業の具体的な数値目標等は定められていない。なお、当該決定においては、「空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であること」も避難指示解除の要件の一つとなっている。
八 ヒアリングで提供された復興庁資料によれば、帰還困難区域を抱える自治体は、飯舘村に加えて、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、葛尾村の計六町村があり、帰還困難区域全体における住民登録数は、飯舘村で二百四十六人、双葉町で五千六百四十四人、大熊町で九千八百六十二人、浪江町で二千九百人、富岡町で三千五百七十二人、葛尾村で百八人おり、計二万人を超えている。
また、環境省がヒアリングで示した事前質問への文書回答によれば、帰還困難区域の対応については飯舘村以外の五町村に関しても「地元の要望を十分に踏まえつつ、政府全体として検討を進めて」いくとのことである。
その五町村は目下、除染の実施を強く求めており、福島県の内堀知事も、自治体との十分な協議をしっかり満たすことが大事である旨を公言していることが報道されている。こうしたことを総合的に鑑みた場合、三密回避のために、住民との会合の開催や協議や合意形成も容易ではないなか、今夏にも解除の方針や要件を見直すことは、現実的ではないと考えるがどうか。
「二、四及び八について」で回答
2020年6月11日原発ゼロの会のヒアリング
3密を回避しながらzoom併用で開催しています。